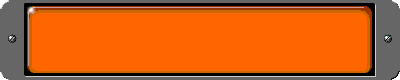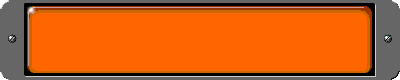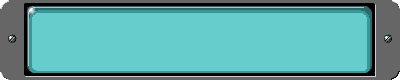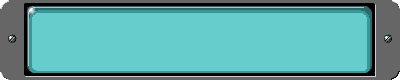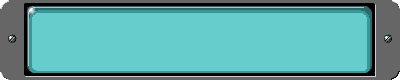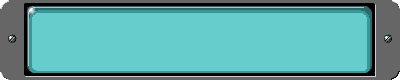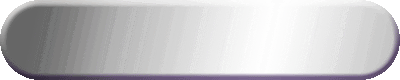①スチールパイプの上に塩化ビニール張り
①と②に関しては紫外線の影響を最も受けやすく、庇の無い場所での使用の場合は、寿命が特に短くなります。また、同じタイプのの古い物干し竿ほど、パイプの肉厚と表面の塩化ビニールの厚みが厚い為に、最近の物の方が、一般的に寿命が短い傾向があります。大まかな目安として20年使われた古い物干し竿の3分の1程度の寿命と思われます。ステンレス製物干し竿の殆んどが、③の巻きステンレスに該当します。これらは磁石が付くことで確認できます。端のキャップが紫外線で割れてしまうと、雨水が中に入って錆びてしまい、洗濯物を汚したり折れてしまう場合も有ります。また、巻いたステンレス板を留めているスポット溶接不良により、ステンレス板がはげてしまうケースも多く見受けられます。つまり、錆びにくい竿として表示して有りますが、決して長持ちする商品では無いようです。
①オールステンレス製(SUS304・磨き指定なし)
②オールステンレス製(SUS304・磨き♯400・高強度)
①は最も普及しているオールステンレス製物干し竿ですが、全体から見ると、まだまだ数パーセント程度の普及率と思われます。最も普及率を妨げている原因は、金物店やホームセンターでの取り扱いが、殆んど無い為と思われます。しかし不思議な事に、伸びるタイプと継ぎ足すタイプのみは取り扱うお店も多いようです。つまり、一本物のみが極端に普及しない商品のようです。そこから業界の不思議な意図を感じるのは私だけでしょうか・・・。さらに不思議な現象は、ステンレス製物干し台の殆んどは、オールステンレス製です。つまり金物店やホームセンターでは、竿は巻きステンレス製で、物干し台はオールステンレス製をセット商品として平気で販売しております。これらの違いは、製作段階で曲げ加工の有無が大きく関係しているように推測されます。つまり、オールステンレス製の物干し竿が特別贅沢な仕様ではない事が分かります。②は普及商品に飽き足らない方に、強い支持を受けています。多くの方はステンレス竿を購入する理由の筆頭は、長持ちする商品として選択されていると思います。実は長持ちする物干し竿の条件として、余裕の強度が大変重要です。30年前の物干しと現在の物干しとの、最も大きな違いは干し方の変化があります。昔はハンガーを殆んど使わずに袖を通したり、竿を覆うように干すのが一般的でした。つまり、現在の何倍かの本数(5~10本程度)の竿を使用していた訳です。しかし、現在は少ない竿(1本~4本程度)にハンガーを利用しながら密集して干す傾向があります。当然のように、竿1本当たりの重量が多くなり、たわんでしまう傾向が顕著になってきています。その結果このような高強度(一般の2倍~4倍)の商品をご希望される方が増えてきています。ただし重量(3.1kg~7.5㎏)が何倍もありますので、竿を移動される方や、袖を通すために片方を度々はずす方には不向きかと思われます。また、磨きに関しても♯400は鏡面仕上げですので、ほこりや汚れが付きにくく、結果として普及品よりも錆びにくいようです。
①アルミ製(ブロンズ色)
①②のアルミ製品は一般的に最も錆びにくい商品と言っても間違いないと思います。アルミ製の商品は表面に錆を防止する為の、人工的皮膜を塗布してあります。皮膜は大変引っかき傷に弱く、修復することができません。つまり、傷が付き易い設定での使用を避けた方が良い商品です。また、強度的な面から、同じ太さのスチール製及びステンレス製の竿と比較して、強度が大変劣ります。つまり同じ太さを選択すると、たわみが大きくなります。一般的には4m竿で直径が35mmが標準とお考えください。 大きな傷をつけなければステンレス竿と比較して圧倒的に錆にくい性質があります。特に竿をあまり水拭きしない方や、周囲に畑が多くて土ぼこりが多い方や、海沿いの方には最も適した竿と思われます。色に関してはサッシやベランダの色に合わせるのが一般的です。ただし、全体の流れとしてはブロンズ色からステンカラーの方にゆるやかに移行しているように思われます。
①固定型
①固定型は竿の両端を紐などで固定して使用する場合は、両端の余裕は必要有りません。逆に余裕が30cm未満の場合は固定する必要が有ります。固定する紐は紫外線に強く、ほどく事を前提した靴紐のような物が最適です。後々錆びてしまう針金は避けるべきです。②否固定型は竿を移動したり、袖を通して干す方に最適です。風が強いと竿がずれて落ちてしまう可能性がありますので、両端のはみ出し余裕を40cm以上取る事や、脱落防止ストッパーの利用をお勧めいたします。